英国の生んだ「奇跡の木製機」といわれるモスキートは、ほとんどが木製で構成されたボディにロールスロイス社のマリーンエンジン2基を搭載した双発機で、操縦士と航法士が並んで座る並列複座式(航法士 席のほうが少しだけ後ろにずれている)のコックピットを持っていた。 席のほうが少しだけ後ろにずれている)のコックピットを持っていた。
1940年にデハビランド社によって武装を持たない高速爆撃機として木製構造で開発したされたこの機体。設計段階では無武装の木製機という先入観からイギリス空軍からは見向きもされなかったが、この構想に自信があったデハビランド社は自主開発で、爆撃機タイプ、戦闘機タイプ、写真偵察機タイプと3種の試作機を完成させ、当時最高速戦闘機のスピットファイアより30m/h以上も速い速度をたたき出しその高性能を証明し、イギリス空軍を驚かせながらも、試作された3種以外にも戦闘爆撃機、先導機(パスファインダー)、夜間戦闘機にも改造され各分野で活躍した名機であった。
戦闘爆撃型のモスキートB.MkⅩⅥの場合の性能緒元では、マリーン77型1710馬力×2のエンジンで最高速度が668km/h、航続距離2,400km、最大爆弾搭載量1,810kg、飛行高度限度11,000mとなっており、ドイツ軍の戦闘機ではMe162しかまともに追いつけない爆撃機である。
この飛行機の優秀性はその機体にありましたが、機体の構造が樺の木を両側にバルサ材を真ん中にサンドイッチしたベニヤ板のモノコック構造であることが、軽くて強度がある機体の秘密でした。又この機体は生産が楽なように縦に2分割され別々に作ってあとから真ん中でくっつける方法を取っていましたので、非常に生産効率が高く維持できる利点もありました。この成果はデハビラント社の木製に関する技術が優秀であり木の特徴を非常によく把握して、木のもつ欠点を出さず長所を充分生かすように、しかも生産面における合理化まで考えた設計であった。
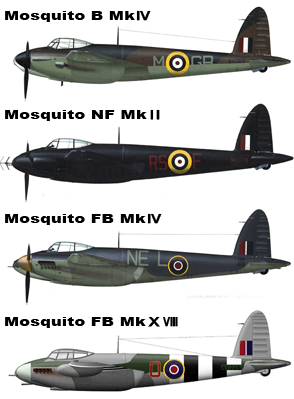 モスキートの各バリエーションの特徴と代表的な形式を見ていきましょう。 モスキートの各バリエーションの特徴と代表的な形式を見ていきましょう。
昼間爆撃機型は最初の量産型(B.MkⅣ)もこのタイプで、胴体内と外翼パイロンに爆弾を搭載し機銃は無搭載でした。昼間爆撃タイプで最も多く生産されたのがB.MkⅩⅥで約1,200機。最終的にこのタイプは1,816
kgのブロックバスター爆弾まで搭載出来るようになります。このタイプは爆弾を搭載せずに戦場偵察にも良く使用され、またチャフ散布機やパスフェンダー(嚮導)機の任務に付くのもほとんどはこのタイプであった。
戦闘機型は、F.MkIIから量産され胴体下に20mm機関砲4門と機首に7.7mm機関銃4門を装備し、やがて対空機上レーダーを機首に搭載した夜間戦闘機型に派生され、NF.MkⅡ、NF.MkⅩⅡが量産された。戦後には対空機上レーダーをさらに強化し機種の形まで拡大されNF.MkⅩⅤシリーズも量産されています。
写真偵察機はPP.MkⅣなどが生産され、カメラを搭載したタイプで、ドイツでMe162が実戦配備されるとその高速優位性は薄れたが、翼を延長し過給機を装備することで、高高度性能を高めて強行偵察を敢行した。
戦闘爆撃型は、FB.MkVIから量産されるようになり、低空進入によるピンポイント爆撃に使用さた。また、対艦攻撃用にロケット弾も8発搭載出来る派生型や、機首に6インチ対戦車砲を備えたFB.MkⅩⅧという派生型も存在した。
フランスのアミアン刑務所の壁と警備員の宿舎を爆撃しレジスタンスメンバーを脱出させたり、ノルウェーのベルゲンにあったゲシュタポの司令部空襲では低高度からの非常に精密な爆撃を敢行し囚人を解放して記録資料を焼き払った等、モスキートならでは戦歴も残しており、 モスキートは何れの任務も他機種で同じ任務を実行した際と比べれば損傷率が低く、そのモスキートの優秀性は終戦まで旧式化する事がなかった程でありました。
そんなモスキートにも欠点がありました。それは熱帯地域での稼働率が著しく低下する事で、原因は木製ボディが湿気に弱いのと、それを合板しているカゼイン系接着剤が劣化、ひび割れて機体外板が剥離し墜落事故を起こし兼ね無い状況であった。
モスキートは1940年から就役したのだから、当然、他国でもモスキートを模倣して優秀な木製機を製作しようとするのは当然の事です。次回コラムはその他国の木製機を紹介して行きます。 |